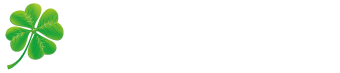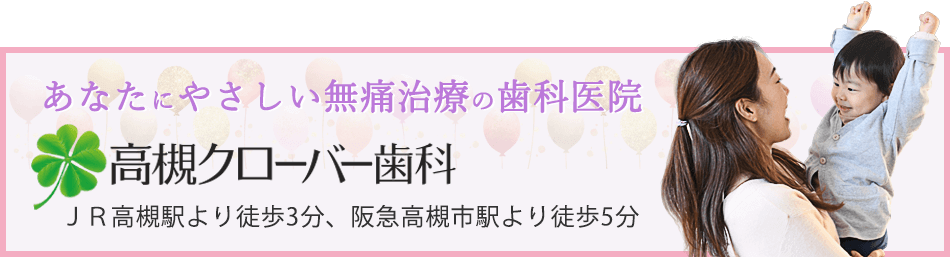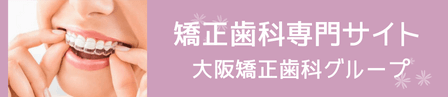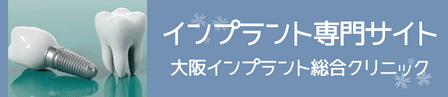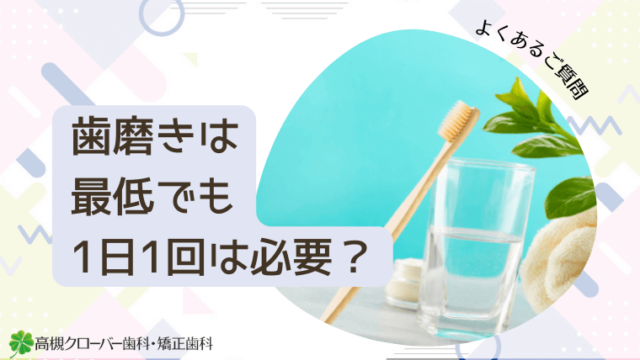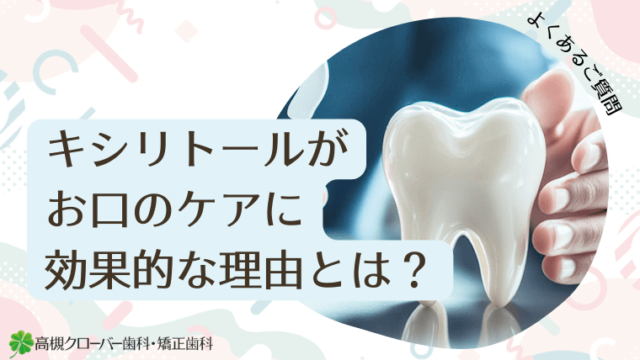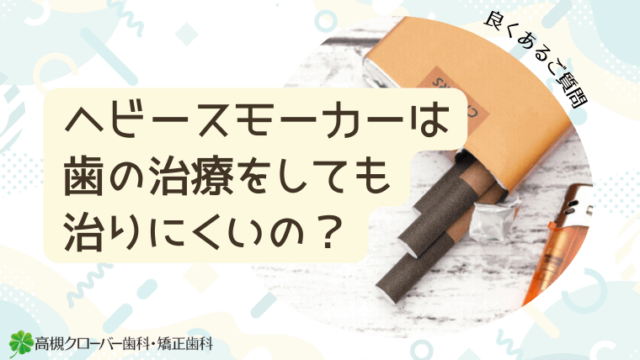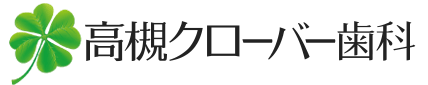親知らずを抜くときの麻酔について知りたい!

「親知らずを抜く」と聞いただけで、ゾワッとしたり、不安になったりする方も多いのではないでしょうか?
「痛くないのかな?」
「麻酔ってちゃんと効くの?」
「抜いた後、どれくらい腫れるんだろう…」
そんな疑問や不安が頭をよぎるのは、当然のことです。特に、歯の治療が苦手な方にとっては、親知らずの抜歯はまさに“試練”のように感じられるかもしれませんね。
でも、ご安心ください。現在の歯科医療では、麻酔の技術がとても進歩しており、痛みを最小限に抑えながら抜歯を行うことが可能です。実は、多くの患者さんが「思っていたよりも痛くなかった!」と驚くほどなんですよ。
この記事では、親知らずの抜歯に使われる麻酔の種類や、どのようにして痛みを抑えるのかについてご説明します。不安を少しでも和らげて、安心して抜歯に臨めるよう、一緒に知識を深めていきましょう!
親知らずを抜く際に麻酔が必要な理由
現代の日本人は顎がとても小さいです。そのため、親知らずがまっすぐ生える方は少なく、斜めや横に生えたり、歯肉の中で生えずに隣の歯を押しているという場合があります。親知らずを抜く際は生える位置の関係から身体への負担が大きくかかります。では、親知らずの抜歯に麻酔が不可欠である理由を挙げていきます。
骨や神経に近い位置にある
親知らずは上下ともに顎の奥深くに生えていることから、神経や血管と接している、もしくは近い位置にあります。そのため、神経や血管を傷つけないよう慎重に手術を行う必要があります。
埋伏歯のケースが多い
骨や歯茎の中に親知らずが埋まっている埋伏歯の方は、歯肉を切開して取り出す手術が必要です。下顎の親知らずが下顎管(神経や血管が走っている部分)の近くに埋まっている場合、歯を割り抜くことがあります。
術中のストレス軽減
麻酔を使用することで患者さんが治療中に余計な緊張を抱えず、快適に抜歯治療を受けられるようになります。
抜歯で使用される麻酔の種類
親知らずの抜歯では、痛みをできるだけ感じないようにするために「麻酔」が使われます。実は、ひとくちに「麻酔」といっても、いくつか種類があることをご存じでしょうか?それぞれの麻酔の特徴を、なるべくわかりやすくご説明しますね。
局所麻酔
特徴:抜歯の際、ほとんどの人が受ける麻酔
これは、抜く部分の周りだけを麻痺させる麻酔です。歯ぐきに注射をして、痛みを感じなくする方法で、親知らずの抜歯では基本的にこの麻酔が使われます。
効果のポイント
- 数分で麻酔が効き始める
- しばらくの間(1〜2時間ほど)、その部分の感覚がなくなる
- 意識ははっきりしているので、先生と会話も可能
よくある疑問:「注射自体が痛いのでは?」
ご安心ください!最近では表面麻酔(塗るタイプの麻酔)を先に使って、針のチクッとした痛みを抑える工夫がされています。
最も一般的なタイプで、一番よく使われる麻酔です。抜歯する部分の周辺の歯茎にまず表面麻酔を塗布します。感覚がなくなったのを確認して、注射でキシロカインなどの薬を直接歯肉へ注入します。患者さんの意識はありながらも、痛みを感じることはありません。ただし、薬は苦いため、味が苦手な方はお口をすすがせてもらいましょう。
笑気麻酔
特徴:麻酔の注射が怖い人におすすめ
「歯医者の麻酔が怖い…」「抜歯のことを考えるだけでドキドキする…」という方に使われることがあるのが、この笑気麻酔です。マスクをつけて、笑気ガス(亜酸化窒素)を吸い込むことで、リラックスできる状態になります。
効果のポイント
- 意識はあるけれど、不安や緊張が和らぐ
- 注射が怖い人にも適している
- 効果が切れるのが早く、施術後すぐに普通の状態に戻る
よくある疑問:「眠ってしまうの?」
いいえ、笑気麻酔は眠る麻酔ではなく、少しフワッとした感覚になって緊張を和らげるものです。
亜酸化窒素という笑気ガスを吸入することでリラックス効果を得る方法です。体内で分解されないため、内臓への負担がかからず子供から大人まで使用できます。鼻から吸入すると夢心地になりますが意識はあります。局所麻酔と併用されることもあり、抜歯治療に対する不安感を軽減します。
静脈内鎮静法
特徴:親知らずを一度に何本も抜く人に使われることが多い
点滴で鎮静剤を入れて、ウトウトと半分眠ったような状態にする方法です。完全に眠ってしまう全身麻酔とは違い、「なんとなく意識があるけど、ぼんやりしている」という感覚になります。
効果のポイント
- 不安や恐怖をほとんど感じずに抜歯できる
- 痛みや音が気にならなくなる
- 施術後の記憶がぼんやりすることが多い
よくある疑問:「全身麻酔とどう違うの?」
全身麻酔は完全に意識がなくなるのに対し、静脈内鎮静法は半分眠ったような状態になります。処置後は少し休む必要がありますが、比較的早く回復できます。
腕の静脈に点滴を用いて、鎮静剤を体内に投与する方法です。半分眠ったような状態で治療を受けられるため、手術への恐怖感が強い方、歯科恐怖症の方に向いています。抜歯を行う歯科医師とは別に、麻酔医が患者さんの全身状態を管理します。
全身麻酔
特徴:入院が必要なケースが多い
これは、病院の手術室などで使われる麻酔で、完全に眠った状態にする方法です。親知らずの抜歯で使われることはほとんどありませんが、埋まっている親知らずを一度に4本抜く場合や、特別な事情がある場合に選択されることがあります。
効果のポイント
- 完全に意識がなくなるので、手術の記憶がない
- 痛みを一切感じない
- 施術後は目が覚めるまで時間がかかる
よくある疑問:「親知らずの抜歯では全身麻酔が必要?」
基本的には局所麻酔や静脈内鎮静法で対応できるため、全身麻酔はごく稀なケースです。
非常にまれではありますが、特に難しい部分に生えている親知らずの抜歯や複数本を同時に抜く場合に使用されます。完全に意識を失った状態で治療を行うことから、自発呼吸ができないため、呼吸するためのチューブを挿入します。抜歯を行う歯科医師とは別に、麻酔医が患者さんの全身状態を管理します。
麻酔の手順と流れ
難しくはない親知らずを抜く場合、安全かつ迅速に処置を行います。では、手順についてご紹介します。
1.事前のカウンセリング
抜歯前に、麻酔の種類や抜歯をどのように行うか、流れについて説明を受けます。不安があればこの段階で歯科医師へ相談しておきましょう。
2.麻酔の準備
口腔内の消毒を行い、注射を行う部分に表面麻酔を塗布します。これにより、注射の針の痛みを軽減できます。
3.麻酔の注射
局所麻酔の場合、歯茎や抜歯予定の歯の周りに注射します。当院では麻酔液を体温位の温度に温め、痛点を外して極細の針で注入を行います。数分後に感覚が麻痺し、痛みを感じにくくなります。
4.麻酔の効果確認
麻酔が完全に効いているかドクターが確認します。感覚が鈍くなるまでは抜歯治療を始めません。
5.抜歯開始
麻酔が効いた状態になれば抜歯が行われます。痛みは感じませんが、歯を抜く際の圧力や振動を感じることがあります。
麻酔が切れた際の痛みとその対処法
効果には個人差がありますが、通常、1〜3時間程度で切れます。切れてくるとこのような症状が現れることがあります。
痛み
抜歯後の痛みは、麻酔が切れると感じられることがあります。歯医者さんでの処方を受けていれば、指示通りに痛み止めを服用しましょう。
腫れ
親知らずを抜いた部分が腫れることがあります。患部の外側の頬からタオルで冷やしてあげれば、腫れを軽減できます。
出血
抜歯後に少量の出血が続くことがあります。ガーゼを上下の歯で噛んで止血を行いましょう。
痛みや腫れは日にちが経過すると引いていきますが、腫れや痛みが増したり、出血が止まらないなどは、すぐに歯科医師に相談することをおすすめします。
親知らずが下顎の神経に近い位置にあるため、歯を抜いた後、下唇のしびれが起きることがあります。日数が経てば消失することがありますが、後遺症になる可能性もゼロではありません。下唇のしびれが二週間経っても同じ程度のしびれであれば、歯科医師へ相談しましょう。
親知らずの麻酔に関する注意点
親知らずの麻酔の際に、どのような点に注意すれば良いでしょうか。
事前に健康状態を伝える
アレルギーや疾患がある患者さんは、事前に歯科医師に伝えることが重要です。疲労がたまっていたり、体調が良くない場合は、麻酔が効きにくくなり、痛みを感じてしまうからです。
麻酔の効きが悪い
炎症が強い場合や個人差によって、麻酔が効きにくいことがあります。日頃からアルコールをよく飲む方は肝臓で分解するための酵素が多く、薬を早く分解してしまうために効きづらいということが考えられます。また、基礎代謝が良い方も同様です。
麻酔後の運転は控える
麻酔や鎮静剤の影響で反応速度が低下するため、治療後は運転を避けるようにしましょう。車はもちろん、自転車なども避けておきましょう。
一時的な神経の麻痺
下顎の親知らずを抜く際、下顎神経に近い場合、一時的にしびれが残ることがあります。また、麻酔を打った後は感覚が分からないため、唇を噛んでしまうことがあります。一時間くらいは出来るだけ飲食を避けておき、治療後の違和感や異常を感じた場合は、早めに医師に相談することが大切です。
アレルギー反応
非常にまれですが、麻酔薬に対するアレルギー反応が出ることはあります。軽度のアレルギー反応が起きる確率は1%あるかどうかです。ラテックスグローブなど他のものに対するアナフィラキシーという可能性もあります。
あなたに合った麻酔を選ぼう!
| 麻酔の種類 | どんな人におすすめ? | 意識の有無 | 効果 |
| 局所麻酔 | 一般的な抜歯 | ある | 抜歯部分のみ麻痺 |
| 笑気麻酔 | 不安が強い人 | ある | リラックスできる |
| 静脈内鎮静法 | 抜歯が怖い人・親知らずを何本も抜く人 | ぼんやり | ほぼ無痛で記憶もあまり残らない |
| 全身麻酔 | 特殊なケース(入院が必要な場合など) | なし | 完全に眠った状態 |
「どの麻酔がいいの?」と迷う方もいるかもしれませんが、基本的には局所麻酔で十分なことがほとんどです。ただ、不安が強い方や抜歯の難易度が高い場合は、笑気麻酔や静脈内鎮静法を検討するのも良いでしょう。
抜歯は決して楽しいものではありませんが、麻酔の力を借りれば、痛みを最小限に抑えて乗り越えられます! 不安なことがあれば、歯科医に相談してみてくださいね。
まとめ

親知らずの抜歯に使用される麻酔について、基本的な情報から具体的な手順、注意点まで詳しくご説明いたしました。親知らずの抜歯は、麻酔を使用することで痛みを抑え、安全に行うことができます。安心して治療を受けるために、歯科医師としっかり相談し、自分に合った方法を選択してください。