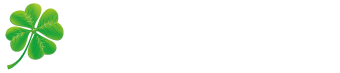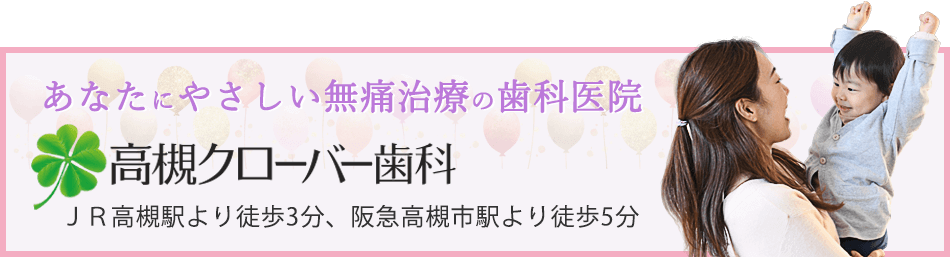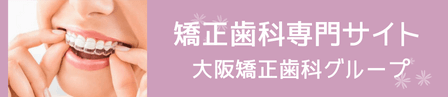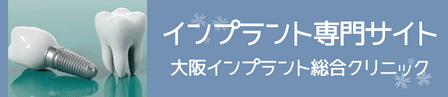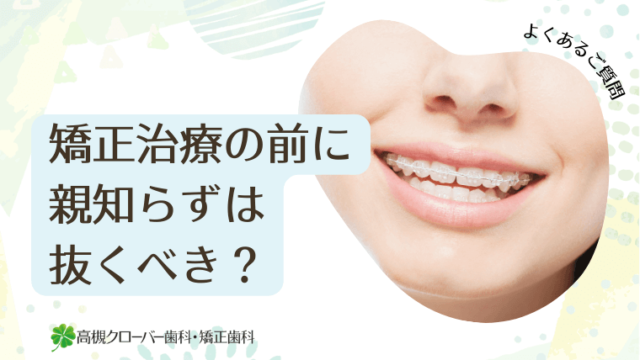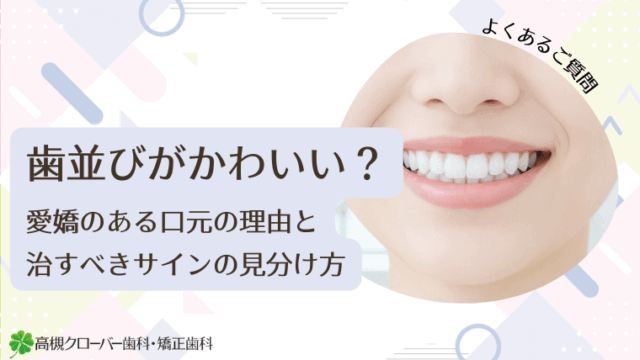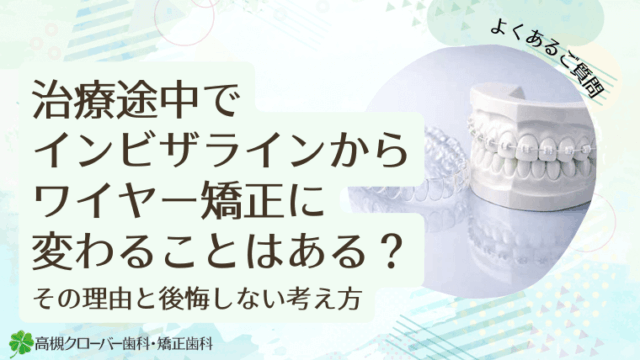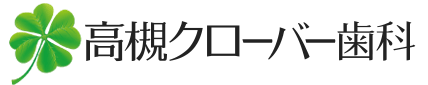正しい舌の位置とは?歯並びに影響ある?
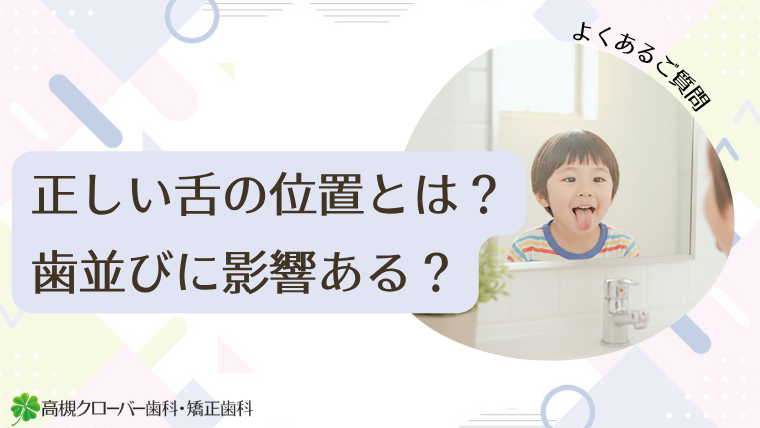
正しい舌の位置とは? 歯並びにどのような影響があるのですか?
正しい舌の位置とは「舌全体が上あご(口蓋)に優しく張り付いている状態」です。この位置が崩れると、口呼吸や歯列の乱れにつながることがあります。整った歯並びや噛み合わせを保つには、舌の位置の理解が欠かせません。

この記事はこんな方に向いています
- 歯並びがガタつきやすい原因を知りたい
- 子どもの口元がポカンと開きがちで心配
- 舌の癖が歯並びに影響するのか知りたい
- 舌トレーニング(MFT)に興味がある
- 将来的に矯正治療を検討している
この記事を読むとわかること
- 正しい舌の位置と間違った舌の位置の見分け方
- 舌の位置が歯並び・噛み合わせに及ぼす影響
- 口呼吸・舌癖との関係
- 今日からできる舌のトレーニング方法
- 子どもと大人で注意すべきポイントの違い
目次
正しい舌の位置はどこ?どうやって確認するの?
正しい舌の位置とは、舌の先だけでなく舌全体が上あご(口蓋)にふんわり貼り付いている状態を指します。舌先は上の前歯の裏の少し後ろ、スポットと呼ばれる位置に軽く触れ、舌の側面や奥までが上あごに沿うように収まります。この姿勢が自然に保てると、気道が広がり、歯並びにも良い影響が生まれます。
舌全体が上あごに収まり、舌先は前歯の裏より少し後ろが正しい位置です。
正しい舌の位置は、口の中のバランスを保つための基本となります。確認するポイントは次の通りです。
正しい舌の位置の特徴
- 舌全体が上あごに触れている
→ 舌の前・中央・奥までが上あごに “吸い付く” ようになっている。 - 舌先がスポットに触れる
→ 上の前歯の裏の少し後ろ(スポット)に舌先が触れる位置。 - 上下の歯は軽く離れている
→ 噛みしめず、上下の歯は1〜2mmほど離れたリラックスした状態。 - 唇は軽く閉じている
→ 「口を力で閉じている」ではなく、「スッと閉じている」自然な状態。
これらは一見小さな違いのようですが、舌の位置は歯並び・噛み合わせ・呼吸に影響するため、習慣として身につけることが重要です。
舌の位置が歯並びに影響するのはなぜ?
舌は思っている以上に強い筋肉で、普段の位置や動きが歯の向きや噛み合わせの形成に影響を与えます。舌が下がり過ぎていると、内側から歯を支える力が弱まり、外側の頬や唇の圧力が勝って歯列が狭くなることがあります。また、舌で歯を押す癖があると前歯が前に出たり、開咬と呼ばれる噛み合わせのズレを生むことがあります。
舌の力や位置は歯の向きに影響し、歯並びの乱れの原因になることがあります。
舌は安静時でも一定の位置と力を保っています。特に影響するのは以下の点です。
舌の位置が歯並びに影響する主な理由
- 舌の力が歯を内側から支えている
→ 舌が低い位置にあると支えが弱まり、歯列が狭まりやすくなる。 - 頬・唇の筋肉とのバランスが崩れる
→ 舌が低い位置のままだと外側からの圧力に負けてしまう。 - 舌で歯を押す癖があると前歯が動く
→ 飲み込みのときに舌が前に出る癖があると前歯が前方へ傾きやすい。 - 気道が狭くなり口呼吸が増える
→ 舌の位置が低いと気道が狭まり、口呼吸になり、口の中が乾燥しやすくなる。
歯並びは「歯そのもの」だけでなく、舌・頬・唇の筋肉のバランスで成り立っています。舌の位置はその中心に位置し、健康的な口元の基礎とも言えます。
間違った舌の癖にはどんな種類がある?
間違った舌の癖は「舌癖」と呼ばれ、歯並びの乱れの原因になります。代表的な舌癖として、前歯を押す癖、舌を下げてしまう癖、左右のどちらかに偏らせる癖があります。これらは無意識で起こることが多く、矯正治療後の後戻りを引き起こす要因にもなります。
舌癖には前押し、低位舌、左右偏位などがあり、歯並びに影響します。
舌癖は本人が自覚していないことが多く、治療の進行にも影響することがあります。
代表的な舌癖
- 前に押す癖(舌突出癖)
→ 飲み込む時に舌が前に出る。前歯が開きやすくなり開咬の原因になる。 - 低い位置に置く癖(低位舌)
→ 舌が常に下に落ちている状態。歯列が狭まり、口呼吸を呼びやすい。 - 片側に寄せる癖(左右偏位)
→ 舌が左右のどちらかに寄る癖。歯列の左右差や噛み合わせの偏りにつながる。 - 舌で奥歯を押す癖
→ 上下の奥歯の位置が乱れ、噛み合わせのズレの原因になることがある。
舌癖があると、矯正治療をしても歯が再び動いてしまうことがあります。舌の癖は「筋肉の習慣」であるため、意識して改善する必要があります。
舌の正しい位置 vs 間違った位置
舌の位置による特徴の比較
| 項目 | 正しい舌の位置(理想) | 間違った舌の位置(舌癖) |
|---|---|---|
| 舌の高さ | 上あご全体にふんわり接している | 低位(下に落ちる)、前方・左右に偏る |
| 舌先の位置 | 上の前歯裏の少し後ろ(スポット) | 前歯に当たる、出る、奥歯を押す |
| 呼吸のタイプ | 鼻呼吸が自然とできる | 口呼吸になりやすい |
| 歯への影響 | 歯列を内側から支え安定する | 前歯が前に出る、歯列が狭くなる |
| 噛み合わせへの影響 | バランスが整いやすい | 開咬・過蓋咬合などの原因になることがある |
| 姿勢への影響 | 頭が前に倒れにくく姿勢が安定 | 頭が前に出る姿勢になりやすい |
| 矯正との相性 | 治療が安定しやすい | 後戻りを招く可能性がある |
正しい舌の位置にある場合、歯並びや噛み合わせが安定しやすく、口呼吸も起きにくい状態が保たれます。一方、間違った舌癖があると歯列の乱れや後戻りのリスクにつながりやすくなります。表で確認するとわかるように、舌の位置は見た目だけでなく呼吸や姿勢にも関わるため、日常的に意識して整えていくことが大切です。
口呼吸は舌の位置を乱し、歯並びにどう影響する?
口呼吸は舌が低い位置に下がり、上あごの成長や歯列に影響することがあります。口が開いたままの姿勢が続くと、頬や唇の力が強まり、歯列が狭くなることがあります。また、口の中が乾燥して歯垢がたまりやすくなり、むし歯や歯肉炎のリスクも高まります。
口呼吸は舌の位置の乱れと歯列の狭窄を招きやすい状態です。
口呼吸は舌の正しい位置が保てなくなる典型的な原因のひとつです。
口呼吸が招く影響
- 舌が下がり、歯列が狭くなる
→ 舌は本来、上あごの成長を促す役割を持つ。口呼吸ではその働きが失われる。 - 前歯が前に出やすくなる
→ 口が開きやすく、唇の力が弱いことで前歯が不安定になる。 - 口の乾燥で歯垢が増える
→ 唾液の働きが弱まり、むし歯や歯周病のリスクが高まる。 - 姿勢の乱れにもつながる
→ 呼吸のしやすさを優先して頭部が前に出やすくなり、全身のバランスにも影響。
口呼吸は「舌の位置」だけでなく「歯並び」「むし歯リスク」「姿勢」まで広く影響します。改善の第一歩は舌の正しい位置を知ることです。
正しい舌の位置に戻すにはどんなトレーニングがある?
舌の位置を整えるためには、舌の筋肉を鍛え、正しいクセを体に覚えさせる舌トレーニング(MFT)が効果的です。舌先・舌全体・飲み込みの動きを段階的に改善していくことで、歯並びの維持に役立ちます。
舌の筋トレ(MFT)で正しい位置を習慣化できます。
ここでは自宅でできる代表的なトレーニングを紹介します。
舌トレーニング(MFT)の例
- スポットに舌先を置く練習
→ 舌先を上の前歯の裏の少し後ろに軽く当てる練習。鏡を見ながら行うと正確にできる。 - 舌全体を上あごに吸い上げる練習
→ 舌を大きく持ち上げ、上あごに密着させる。数秒キープして繰り返すと筋肉が鍛えられる。 - 唇を閉じて鼻呼吸を維持する練習
→ 鼻呼吸が習慣化すると舌が自然と上に収まりやすい。 - ゆっくり正しく飲み込む練習
→ 舌が前に出ず、上あごに沿うように動く飲み込みを意識して行う。
舌の動きは筋トレと同じで、毎日の積み重ねで改善します。続けるほど正しい舌位が自然になり、歯並びの安定にもつながります。
子どもと大人で舌の位置の影響は違う?注意点は?
成長期の子どもは舌の位置が骨の成長に大きく影響します。一方、大人は骨格の成長は止まっていますが、舌癖があると歯の位置が動き、矯正治療後の後戻りの原因になります。どちらの年代も舌の位置を整えることで口の中のバランスが保たれます。
子どもは成長に、大人は歯の安定に舌の位置が大きく関わります。
子どもと大人では「舌の位置がもたらす影響の範囲」が異なります。
子どもの場合
- 上あごの成長に舌の力が関与する
- 口呼吸や低位舌が長引くと上あごが狭くなる
- 骨格ごと歪む前に改善したほうがよい
大人の場合
- 歯の位置が動きやすく、前歯が不安定になりやすい
- 矯正治療後の後戻りのリスクが高まる
- 舌癖の改善が歯並びの安定につながる
- 年齢にかかわらず、舌の位置は「歯並びの揺らぎ」を防ぐ大切な要素です。
矯正治療中・治療後に舌の位置が重要とされる理由は?
矯正治療では歯が動きやすく、舌の癖があると治療計画に影響することがあります。治療後も舌癖が残ったままだと後戻りが起きやすいため、舌の位置の指導が重視されます。保定期間に舌の位置を整えることが安定につながります。
矯正の成功と安定には舌の正しい位置が欠かせません。
矯正治療で歯を動かす間は、舌の癖が悪影響を与える可能性があります。
矯正における舌の位置の重要性
- 治療中に歯が予定外の方向へ動くのを防ぐ
→ 舌が前に出る癖があると前歯が動きやすい。 - 治療後の後戻りを防ぐ
→ 舌の習慣が変わらないと歯が安定しない。 - 保定期間の効果を高める
→ 保定装置と舌の位置が揃うことで歯列が固定されやすい。
矯正治療は「器具で歯を動かすこと」だけではなく、「正しい舌の位置を習慣化すること」まで含めて初めて安定した結果につながります。
まとめ
舌の位置を整えることは歯並びケアの基礎習慣となります
舌の位置は、歯並び・噛み合わせ・呼吸・姿勢に影響する重要な要素です。「正しい舌の位置」という、いわば口元の基本姿勢を整えることは、健康的な歯並びを長期的に保つための大切な習慣です。
- 舌は上あごに収まるのが自然
- 舌癖は歯並びを乱す原因
- 口呼吸は舌の位置を低め、歯列に影響
- トレーニングで改善は可能
- 矯正治療の安定にも欠かせない
舌の位置は日常の小さな習慣の積み重ねで変わります。
今日から意識を少しずつ変えて、健康的な口元づくりを進めてみてください。
関連ページ:高槻クローバー歯科・矯正歯科の矯正治療