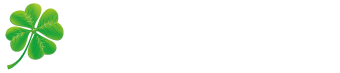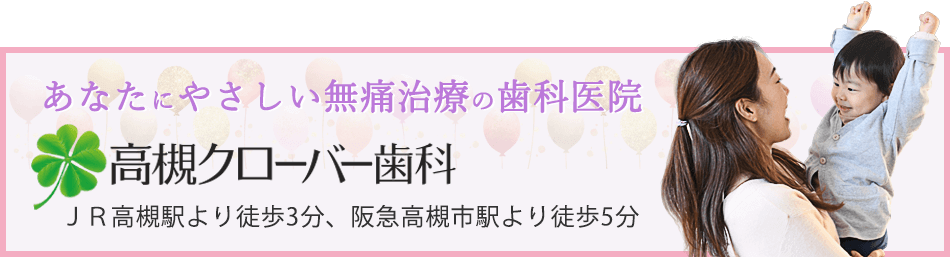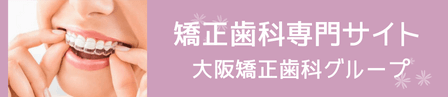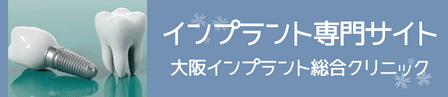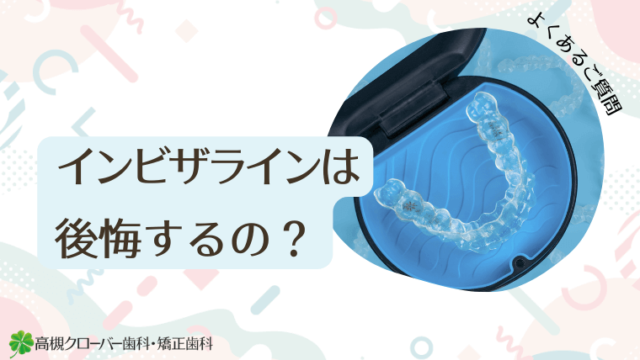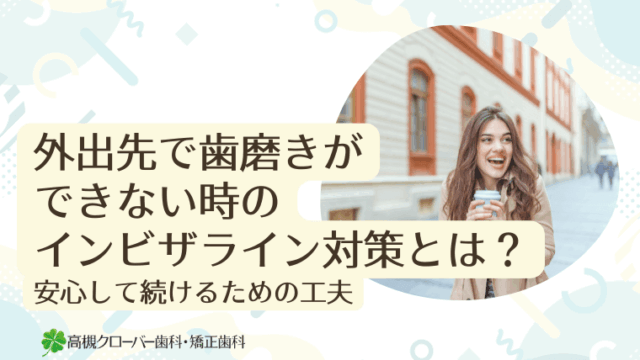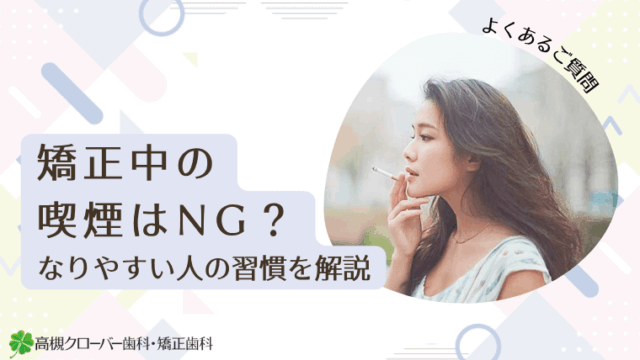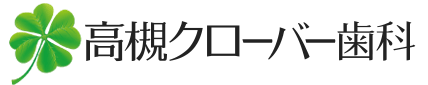矯正中に歯茎が腫れる・下がる?よくある歯茎のトラブルとその対策
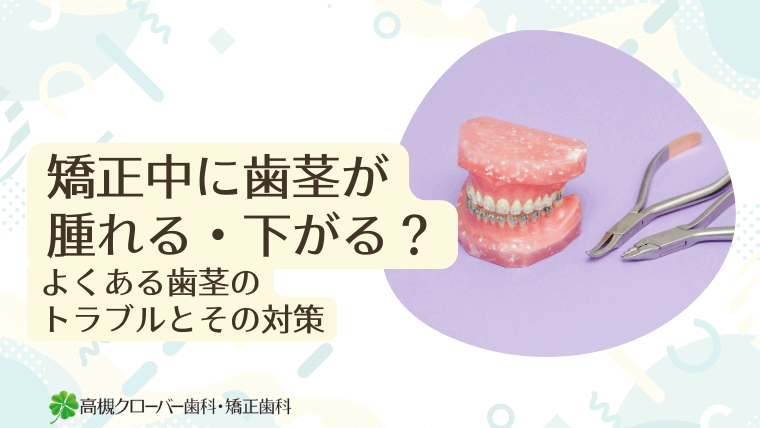
矯正中に気になる歯茎の異変…それ、放っておいて大丈夫?
「なんか最近、歯茎が腫れてきた気がする…」「歯磨きのたびに血が出るんだけど…」
矯正治療をしていると、こうした歯茎の変化に気づくことがあります。せっかく歯並びをキレイにしようとしているのに、歯茎のトラブルが起きたら心配になりますよね。
でも大丈夫。こうしたトラブルは決して珍しいことではなく、正しいケアと知識があればしっかり予防も対処もできますよ。
目次
歯茎のトラブルを放置すると起こるリスクとは
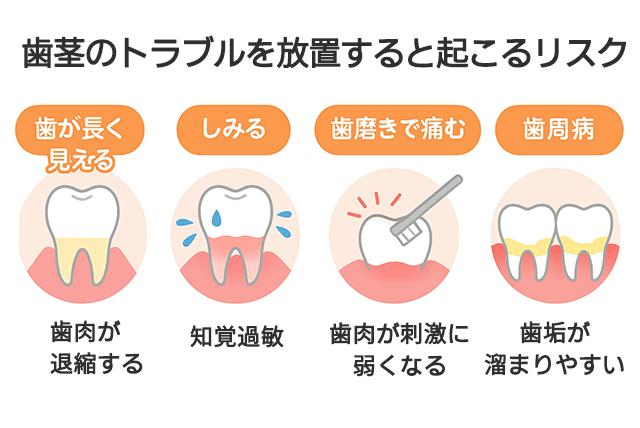
放置してしまうと、矯正治療の効果に悪影響を与える可能性もあります。
歯周病の進行
→ 歯垢が溜まりやすくなり、歯茎の腫れや出血から歯周病へと進行することがあります。
歯茎の退縮(歯茎が下がる)
→ 歯が長く見えるようになったり、知覚過敏を感じやすくなったりします。
矯正治療の遅れや中断
→ 炎症がひどくなると、矯正装置を一時的に外さなければならないことも。
これらのトラブルは、治療の計画にも影響を与えかねません。早めの気づきと対策が大切です。
なぜ矯正中は歯茎がトラブルを起こしやすいの?
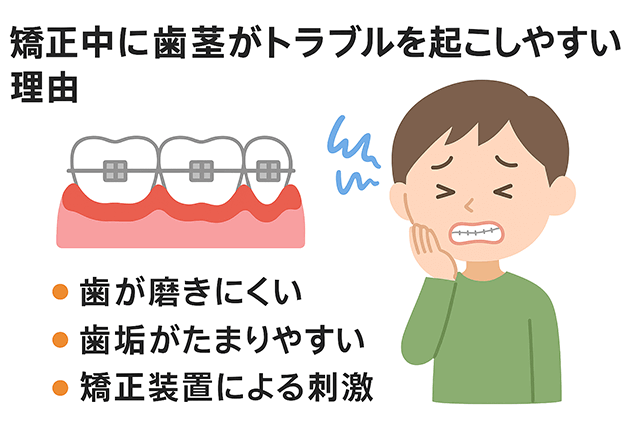
矯正中は、歯に装置が付くことでお口の中の環境が大きく変化します。以下のような理由から歯茎がトラブルを起こしやすくなるのです。
歯垢がたまりやすい
→ 装置の周りに歯垢が付着しやすく、歯磨きがしにくいため汚れが残りやすいです。
力がかかることで歯茎に負担がかかる
→ 歯が動く過程で歯茎にも負担がかかり、一時的に炎症が起こることがあります。
口呼吸による乾燥
→ 装置の違和感で口呼吸が増えると、口腔内が乾燥しやすくなり、歯茎の炎症が起きやすくなります。
その結果として、腫れ、出血、下がりといった症状が出てくることがあるんですね。
ワイヤー矯正とマウスピース矯正、歯茎への負担の違いは?
「ワイヤー矯正とマウスピース矯正、どっちが歯茎に優しいの?」
そんな疑問をお持ちの患者さんも多いですよね。どちらも歯を動かして理想の歯並びを目指す矯正方法ですが、歯茎への影響やトラブルの起こりやすさには少し違いがあります。
それぞれの特徴を比べてみよう!
矯正方法 歯茎への影響 歯磨きのしやすさ 歯垢のたまりやすさ 口内炎のリスク
ワイヤー矯正 金属やブラケットが歯茎に当たりやすく、炎症を起こしやすい 装置が邪魔になって磨きにくい 高い 高い(特に初期)
マウスピース矯正 装置の縁が歯茎に触れて刺激を与えることもあるが、比較的やさしい 取り外せるため、しっかり磨ける 低め 少なめ
こんな違いがあるよ!
ワイヤー矯正は「装置による刺激」が主な原因で歯茎トラブルが起きやすい
特にブラケットが歯茎に近い位置にある場合、ちょっとした刺激でも腫れやすくなることがあります。

マウスピース矯正は「自己管理の甘さ」が歯茎トラブルにつながることも
マウスピースの装着時間が短かったり、清掃が不十分だと歯垢が溜まり、歯茎の炎症に。
 マウスピース インビザライン
マウスピース インビザライン歯磨きのしやすさはマウスピースに軍配!
取り外せるから、しっかり歯磨きができて、歯垢の蓄積を防ぎやすいです。
まとめると…
- それぞれの矯正方法には、歯茎に対する負担の「質」に違いがあります。
- ワイヤー矯正は、装置が直接歯茎に当たることで炎症を起こしやすい
- マウスピース矯正は、清掃不良や装着時間不足による間接的なトラブルに注意
どちらにしても、大切なのは“歯垢をためないこと”と“早めの受診”です!
自分のライフスタイルやケアのしやすさを考慮して、最適な矯正法を選びましょう。
歯茎が下がるってどんな感じ?
「最近、歯が長く見えるような気がする…」
「歯の根元が露出してきたみたいで、しみる…」
そんな違和感を覚えたら、それは歯茎が下がっているサインかもしれません。
歯茎が下がることを「歯肉退縮(しにくたいしゅく)」と呼び、矯正治療中に起こることもあります。
歯茎が下がるとどうなるの?
歯が長く見える
→ 歯の根元部分(セメント質)が見えてくることで、見た目に違和感が出ます。
冷たいものがしみる(知覚過敏)
→ 歯の根元はエナメル質で守られていないため、温度刺激に敏感になります。
歯ブラシが当たるとチクチク痛む
→ 露出した部分はやわらかくデリケートなので、物理的な刺激でも痛みやすくなります。
歯周病リスクが上がる
→ 歯垢がたまりやすくなり、歯周病の原因にもつながります。
これらの症状は、初期のうちは軽い違和感程度ですが、進行すると見た目の悩みや食事のストレスにつながることも。特に前歯など目立つ場所で起こると、心理的な影響も大きいです。
なぜ歯茎が下がるの?
矯正中に歯茎が下がる原因は複数あります。
- 矯正による歯の移動スピードが速すぎる
- 歯茎がもともと薄く、弱い構造をしている
- 強い歯磨き圧や間違った磨き方
- 歯周病の進行による歯槽骨の吸収
つまり、力の加わり方やセルフケア、元々の歯茎の状態が影響してくるんですね。
歯茎が下がると、見た目や感覚面での不快感、さらには歯周病のリスクも高まります。矯正中は特に注意が必要です。
でも安心してね。早めに気づけば、進行を止めたり回復を促すケアも可能です。「あれ?」と思ったら、すぐに歯科医院へ相談してね!
矯正中の歯茎を守る5つの対策
歯茎の健康を守るために、今日からできる対策を紹介します。
1. 正しい歯磨き方法を身につける
専用の矯正用歯ブラシやワンタフトブラシを活用して、装置のまわりまでしっかり磨きましょう。矯正中に虫歯になってしまうと、一時的に装置を外す必要があるなど、治療期間に影響が出る場合があります。
2. フロスや歯間ブラシで細かい部分のケアを
歯と歯の間にたまりがちな歯垢をしっかり除去するのが大切です。セルフケアはとても重要なので、毎日丁寧に行いましょう。
3. 口腔内を乾燥させない工夫を
できるだけ鼻呼吸を意識し、水分をこまめにとるようにしましょう。口呼吸になると、どうしても口内が乾燥して細菌が繁殖しやすくなり、口内環境が悪くなります。
4. 定期的な健診を受ける
歯科医院でのプロのチェックとクリーニングは、トラブルの早期発見・予防につながります。歯垢や歯石は問題が起こる前にクリーニングで除去しましょう。
5. 異変に気づいたら早めに相談する
「ちょっと変かも?」と思ったら、遠慮せず歯科医院へ。初期段階ならすぐに対処できます。大きな問題になる前に早め早めに行動しましょう。
これらの習慣は、矯正中だけでなく、その後の歯の健康維持にもつながりますよ。
まとめ
早めの対処で安心して治療を進めましょう
「歯茎のことって、つい後回しにしがち…」という方もいらっしゃるかもしれません。でも、歯茎は歯を支える大事な土台です。矯正治療で整った歯並びを長く維持するためにも、歯茎の健康を守ることはとても大切。
毎日のケアをちょっと丁寧にして、トラブルが起きる前にしっかり予防していきましょう。
こんなときは歯科医院に相談を!
以下のような症状があるときは、自己判断せずに歯科医院に相談をおすすめします。
- 歯磨きのたびに血が出る
- 歯茎が赤く腫れている
- 歯が長く見えるようになった
- 口臭が強くなってきた
- 痛みや違和感が続いている
これらは歯茎トラブルのサインかもしれません。矯正治療をスムーズに進めるためにも、早めの対応が大事です。