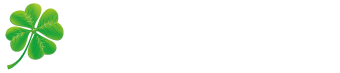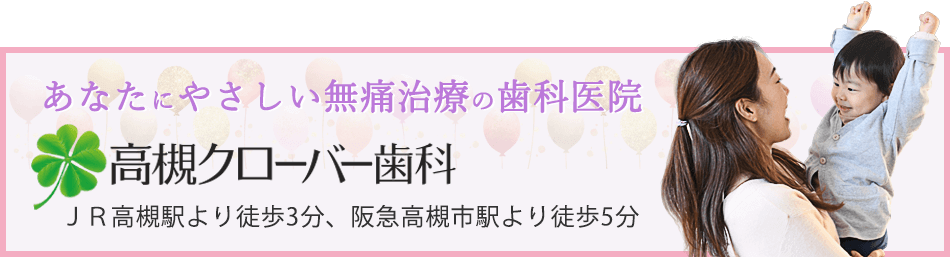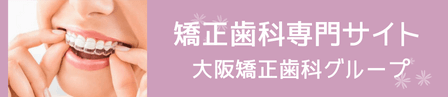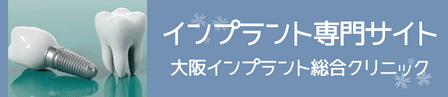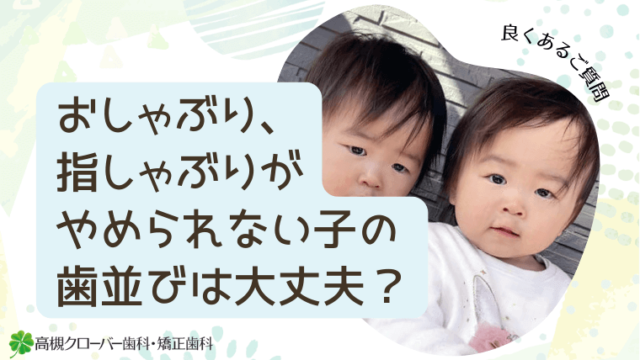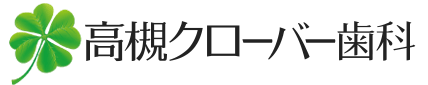乳歯の歯並びが悪いとどうなる?将来のリスクと早めの対応のすすめ
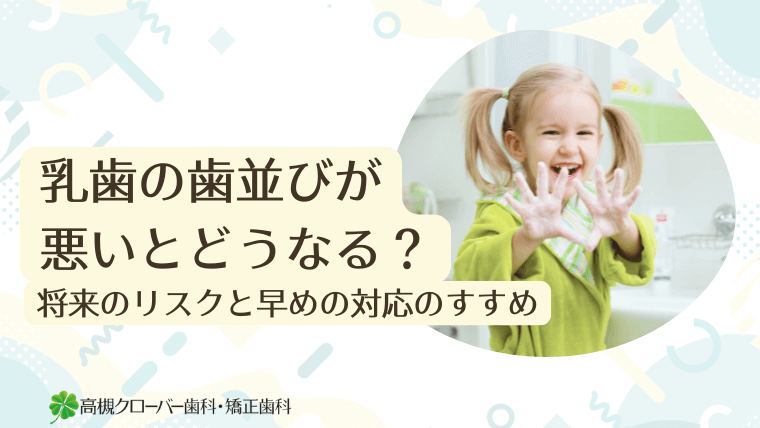
「乳歯の歯並びが悪いと将来どうなるの?」
このような不安を抱える親御さんは少なくありません。乳歯はそのうち抜けるからと軽視されがちですが、じつは将来の歯並びや噛み合わせ、さらには全身の健康にも影響を与える大切な存在です。
この記事はこんな人におすすめ
- 子供の歯並びが気になる方
- 「乳歯はそのうち抜けるから問題ない」と考えている方
- 将来の矯正治療をできるだけ避けたい方
この記事でわかること
- 乳歯の歯並びが悪いとどんなリスクがあるのか
- 具体的な将来への影響とその例
- 対処のタイミングと方法
目次
永久歯にも影響!乳歯の歯並びの重要性
乳歯の歯並びが乱れていると、永久歯が生えるスペースが確保できず、不正咬合になる可能性が高まります。歯が重なったり、ねじれて生えたりすることで、見た目だけでなく機能面にも支障をきたします。
乳歯の歯並びは、永久歯の道しるべです。
具体的な問題点
- 永久歯が正しい位置に生えない
- スペース不足で歯並びがガタガタに
- 永久歯の位置異常(叢生・交叉咬合 など)
乳歯でよくみられる不正咬合
- 叢生(そうせい) → 歯が重なり合ってでこぼこに並ぶ状態。歯磨きがしにくく、歯垢がたまりやすくなる。
- 交叉咬合(こうさこうごう) → 上下の歯がずれて交差してしまう咬み合わせ。
- 正中離開(すきっ歯) → 中央の歯の間が開いてしまう状態。発音にも影響が出ることがある。
こうした問題は、乳歯の歯並びによって「将来の不正咬合の芽」が育ってしまうということを意味します。
あごの成長や噛み合わせにも悪影響
歯並びが乱れていることで、偏った噛み方や筋肉の使い方が続くと、あごのバランスが崩れ、将来的に咬み合わせのズレや顔の左右非対称が生じる可能性があります。
噛み合わせの乱れは、あごの成長に悪影響があります。
よくあるケース
- 片側ばかりで噛む癖がついてしまう
- あごが左右非対称に発育
- 顎関節に負担がかかる
偏った咀嚼は筋肉の使い方にも影響を及ぼし、あごの骨の発育バランスを崩してしまいます。これは成長期の子どもにとって、とても大きな問題です。
発音・食べ方のトラブルにもつながる
歯並びや噛み合わせは、発音や食事の仕方にも深く関わります。舌や唇の動きが妨げられると、正しい発音ができなかったり、うまく噛めないことがあります。
歯並びは「話す・食べる」にも影響します。
よく見られる症状
- サ行・タ行の発音が不明瞭になる
- 食べ物をうまく噛み切れない
- 噛み合わせが悪く、偏食気味になる
乳歯の歯並びは、ただの見た目の問題ではなく、子どもの「ことば」と「食べる力」の成長にも大きく関わっています。
早めの対策で将来の不安を減らす
乳歯の歯並びの異常に気づいた時点で専門的なチェックを受けることで、矯正治療のタイミングを逃さず、より軽度な処置で済む可能性が高まります。
気づいたらすぐ相談しましょう。
早めの対応で期待できること
- 将来的な矯正治療が不要、または軽度に済む
- 骨格の発達に合わせた自然な改善が可能
- 患者さん本人のストレスも少ない
歯科医による定期的な健診は、こうした早期発見のカギとなります。
健診と家庭での気づきがカギ
歯科医院での定期的な健診と、親御さんによる毎日の観察が乳歯の歯並び異常を早く発見するポイントです。「様子見」で済ませず、少しでも気になったら相談を。
親の気づきが未来を守る。
チェックポイント例
- 歯が極端に重なっている
- 前歯のすき間が広すぎる
- 食べ方や発音に違和感がある
- 口呼吸のクセがある
日常の中で気になるサインがあったら、迷わず歯科医院へ相談するのがベストです。小児歯科や矯正専門医による判断で、最適な対応が選べます。
クセや口呼吸が歯並びを乱す原因に
乳歯の歯並びが悪くなる背景には、口呼吸や舌の位置・使い方のクセが関係していることもあります。これらの癖は骨格の発育にも関与するため、早めに見直すことが大切です。
「呼吸や舌の使い方」も歯並びに影響があります
よくある悪習癖の例とその影響
- 口呼吸 → 鼻ではなく口で呼吸することで、舌の位置が下がり、上あごが発育不足になることがある
- 低位舌(ていいぜつ) → 舌が常に下にあるクセ。歯が内側から押されないため、上あごが狭くなる
- 舌突出癖(ぜつとっしゅつへき) → 飲み込むときや話すときに舌が前に出てしまうクセ。前歯を押し出して不正咬合につながる
親ができるチェック方法
- 口をぽかんと開けていることが多い
- 寝ているときにいびきをかいている
- 食べ物をよくこぼす、飲み込むのが下手
- 話すときに舌が歯の間から見える
こういった「癖」は無意識に続いていることが多く、歯並びだけでなく顔の輪郭や姿勢にまで関係してくることもあります。小児歯科や小児耳鼻科、口腔筋機能療法(MFT)の専門家と連携しながらサポートしていくのが理想です。
乳歯期からできる矯正治療とは?
乳歯の段階でも矯正治療は可能です。「永久歯が生え揃ってから」と思われがちですが、あごの成長を利用できる乳歯期の矯正には大きなメリットがあります。
乳歯期に行われる矯正の特徴
- 成長段階のあごにアプローチしやすい
- 装置が簡易的で本人への負担が少ない
- 永久歯が正しく生えるスペースを作る目的で行う
- 将来的な本格矯正の必要性を減らせることもある
代表的な装置例
- 床矯正装置(しょうきょうせいそうち) → あごを広げてスペースを確保する可撤式装置(取り外し可能)
- ムーシールドなどの機能的装置 → 反対咬合(受け口)の早期改善に使用される
永久歯がきれいに並ぶ「土台」をつくるのが乳歯期の矯正です。骨の柔らかい成長期ならではの治療効果が期待でき、心身への負担も比較的少なく済みます。
ただし、すべてのケースで必要というわけではないので、歯科医院での正確な診断が前提となります。
まとめ
乳歯の歯並びの悪さは「いずれ抜けるから」と放置してしまうと、将来の永久歯や噛み合わせ、さらには食生活や発音までに幅広い影響を及ぼします。
将来の大きなトラブルを防ぐためには、「気づいたとき」が行動のタイミング。
親のちょっとした気づきと定期的な健診が、子供の明るい笑顔と健康を守る第一歩になります。
乳歯の歯並びが悪いと起きる影響
| 影響の種類 | 内容と具体例 |
|---|---|
| 永久歯への影響 | スペース不足で歯並びが乱れる、叢生・交叉咬合など |
| 噛み合わせの異常 | あごの成長バランスが崩れる、片側噛みなどの癖がつく |
| 発音や食べ方への影響 | サ行の発音が不明瞭、食べにくさによる偏食、飲み込みの問題など |
| 矯正治療のリスク | 将来の治療が複雑・長期化するおそれあり |
| 心理的影響 | 見た目が気になり自己肯定感の低下につながることもある |